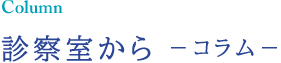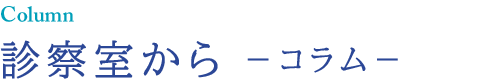宮城県大崎市三本木町の呼吸器科・アレルギー科・内科
- 文字サイズ変更



頑固な咳
2020年1月27日掲載
遅ればせながら新年のご挨拶も申し上げます。
コラムも開始から今年で8年になりました。話すタネも尽きた感があります。
そこで、このコラムを始めるにあたって、最初のタイトルが“長引く咳”でした。
今回は再度“頑固な咳”とタイトルを新たに咳について考えてみます。
いったん風邪をひいたら咳が2週間も3週間も続いて夜もろくろく眠れないという
経験をお持ちも方はたいへん多いのではないでしょうか?
もともと咳というのは異物を吸い込むことで気管や気管支が痙攣を起こして
なんとかその異物を吐き出そうとする、体に備わった大切な防御作用です。
異物にはタバコの煙や粉塵、風邪や気管支炎、肺炎などを引き起こすウイルスや細菌も含まれますね。
ですから、咳はインフルエンザや風邪が重症化しないように気道(空気の出入り口である気管や気管支さらには肺に達する末梢までの細気管支、呼吸細気管支)が懸命に頑張っているのだ、と言えます。
タンがたくさん出て苦しいのでなんとか咳を止めて欲しいのに!というお気持ちはよくわかります。
といってもタンを出すために咳が出ているので、話はそう容易ではありません。
寝たきりのご老人は誤嚥による肺炎が、重症化してやがて死につながることはご存知でしょう。
ですから咳をすることによりタンを可能な限り出すことで(喀出といいます)気道をきれいにすることご縁性肺炎の最大の予防なのです。
咳を積極的に止めるより、まず咳が出る原因の探究が第一です。
咳やたんが続いて熱があったり喉や鼻の症状がある時は、症状が軽微であれば経過をみます。
しかし症状が重篤であればもちろんレントゲンを含めた検査を行い病名を確定していきます。
肺炎、特に若年者ではマイコプラズマ肺炎は激しい咳が特徴的ですし、肺癌や間質性肺炎などがみつかるかもしれません。
最近は肺結核も決して稀でなく要注意です。
しかし、レントゲンや、一般検査でも特に異常がなく、咳が2週間くらい続く場合一番多いのは風邪やインフルエンザなど気道感染によることが多いとされています。
とはいってもそれ以上続く時は咳喘息をまず考えます。
咳喘息は気管支喘息の軽症型に分類されますがその機序はアレルギーといわれています。
最近は呼気ガスの一酸化窒素の濃度を測るという簡便な検査がありますし、そのほかのアレルギー検査さらには肺機能検査などで、咳喘息が強く疑われればと抗アレルギー剤の吸入療法を指導します。
他には副鼻腔炎や逆流性食道炎なども慢性的に頑固な咳をきたすことがあります。
いずれも診断がつけば対応は難しくありません。
最後に忘れてはならないのはタバコです。
習慣的な喫煙者の方にはタバコは異物の最たるものですから、咳止めよりまずは禁煙ということになります。
原因不明の慢性の咳は結構あるものです。
特にさしたる病気がなければいずれ軽快するものですのですから、あまり不安になる必要はないと思います。
しかし、ありふれた症状でありながら、上にあげた病気以外にも沢山見逃してはいけない病気もありますので一度は精査が必要を思います。