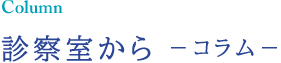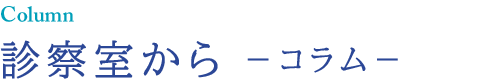宮城県大崎市三本木町の呼吸器科・アレルギー科・内科
- 文字サイズ変更



5人に一人の慢性腎臓病
2025年3月26日掲載
慢性腎臓病をご存知ですか?
英語の頭文字から医療関係者はCKDとも呼んでいます。
慢性に進行する腎疾患を慢性腎臓病と言います。以前は腎臓疾患の多くは慢性糸球体腎炎でしたが、近年は透析患者さんの過半数を糖尿病による糖尿病性腎症(特にDKDと言います)が占めています。ついで高血圧による腎硬化症も増加しつつあります。
これらは生活習慣病によるものが大半です。
我が国では糖尿病はおおよそ、40歳以上で10人に一人、高血圧は60歳以上では二人に一人以上、慢性腎臓病(以後CKDと呼びます)は5人に一人といわれます。 CKDは無症状でしかもゆっくりと進行していきますが、ある段階から急速に増悪し最終的には末期腎不全となり人工透析の導入となる病気です。
CKDは自覚症状に乏しいので健診での尿検査が極めて重要です。もし尿タンパクが(±)なら、要注意ですので、受診を勧めます。(+)以上は必ず受診してください。
糖尿病の方では初期の段階から尿中の微量アルブミン検査の測定が必要です。定期的に尿中アルブミンを測定して腎症の予防に努めましょう。
また健診の際に採血で本人の糸球体濾過量(eGFR)を調べることで腎機能の障害の程度を調べることができます。このGFRは数値によって正常のG1から末期腎不全のG5まで区分分けされており自分の腎機能はどのレベルにあるか知ることができます。
人工透析患者さんは大崎・栗原地区では800人とも言われており、しかも70歳代の高齢者が多く、日常生活に与えるストレスは極めて大きいと思います。
これまで末期腎不全には、ほとんど人工透析が導入されていました。しかし、最近は非常に画期的な処方薬が開発され治療に使われるようになりました。糖尿病薬や降圧剤、抗コレステロール薬も進歩が著しい。これらを使いこなすことによってCKDもかなりの程度コントロールが可能になってきたのです。実際、ここ数年、人工透析導入の減少が見られます。
現在、大崎市と医師会ではCKDの患者さんの重症化予防、透析導入を減らすため、かかりつけ医と腎臓専門医、糖尿病専門医との連携を進めております。CKDの背景には生活習慣の影響がありますので、食事や運動など多職種の医療保健スタッフとの連携も大事です。
慢性腎臓病は腎障害だけでなく心不全、高血圧、貧血、骨粗鬆症など様々な病気に関わっています。自覚症状がないだけにまずは機会をみて特定健診でも職場健診でも健康診断を積極的に受けてください。蛋白尿だけでもかかりつけ医にご相談ください。若いうちから
CKDにご注意ください。
理事長 近江 徹広